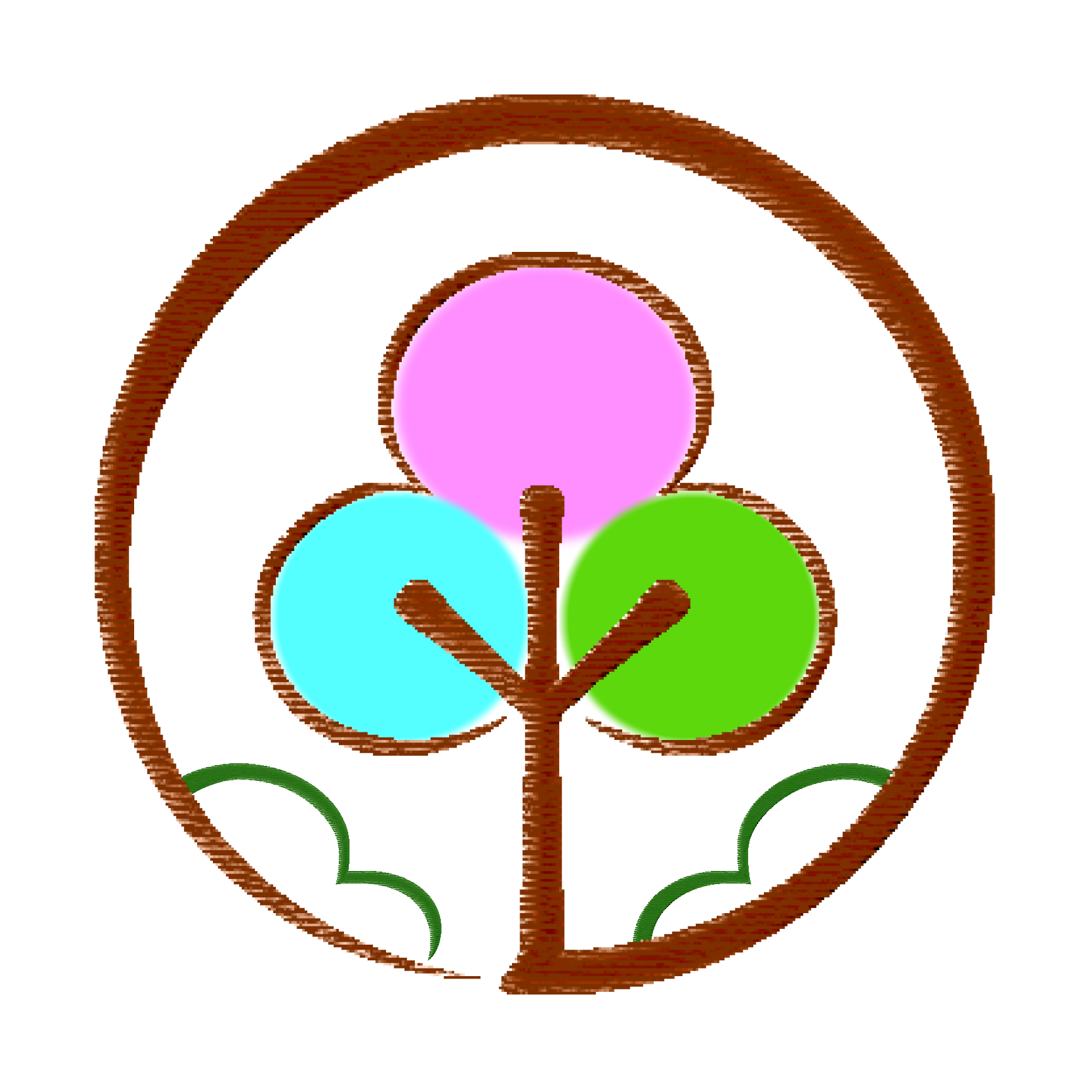先日、エコアクション21の審査員試験を受験してきました。
いざ勉強を始めようにも、最新の過去問や問題集は市販されておらず、まさに雲をつかむような状態からのスタート。「一体どんな問題が出るんだ…?」と、とても不安でした。
そこで私が実際にエコアクション21の審査員試験を受験した経験を基に、審査員試験のリアルな出題内容から、合格ラインを突破するためのピンポイント攻略法までお伝えします。
これからエコアクション21の審査員試験に挑戦する方の、一助になれば嬉しいです。
試験のリアルな難易度と形式
まず、試験は 120分で100問 を解くCBT方式です。
単純な選択式問題だけかと思っていたのですが、キーボードで入力する記述問題も何問かあり、これが想像以上に難しく感じました。
知っているか知らないかを問う単純な問題も多いので、時間には困ることはありませんでした。
古い過去問はやるべき? → 結論:やるべき
公式サイトでは、平成21年と22年の過去問のみが公開されています。「情報が古すぎるのでは?」とためらいましたが、結果的にやっておいて本当に良かったです。
もちろん、ミレニアム開発目標(MDGs)のような今では使われない知識も出てきます。
しかし、そこから「この時代でこれだけ出ているのであれば、その後継であるSDGs関連は多めに出題されるだろう」と予測を立て、知識を補強することができました。
問題の形式や問われ方の傾向は今も近いものが多いので、時間がある方はぜひ一度目を通しておくことをお勧めします。
【分野別】出題内容とピンポイント勉強法
ここからは、私が肌で感じた出題割合と、具体的な中身、そして「これをやっておけばよかった!」という勉強法を解説します。
環境法令(体感60%):この参考書で7割カバー
試験の半分以上を占める最重要分野です。
『図解でわかる!環境法・条例 -基本のキ-』という本を熟読することで、ここの7割程度は解けたという感触です。
事業者が関わる主要な法律の基本が、非常に分かりやすくまとまっています。
エコアクション21でも推奨されているテキストなので、素直にこれを読むことをお勧めします。
具体的な法令の名前を問われる記述問題があったのを記憶しています。
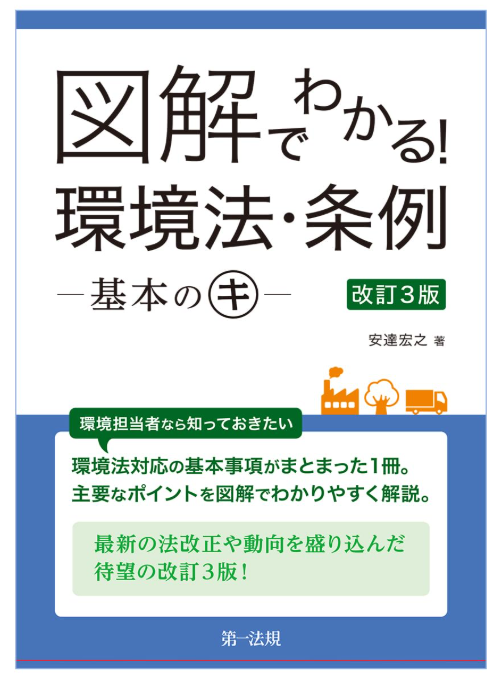
エコアクション21制度(体感35%):暗記が鍵
制度の根幹を問う問題です。
暗記で乗り切る部分が多いと感じました。
ガイドライン 認証・登録制度 審査および判定規則の3つに分けて解説します。
ガイドライン
PDCAサイクルを構成する**「14の要求事項」は、全て覚えて**いきましょう。単語を覚えるだけでなく、「それぞれの要求事項が、具体的に何を求めているか」という流れを問う記述問題が出題されました。テキストを読み込み、流れを自分の言葉で説明できるようにしておくと万全です。
認証・登録制度
ここはそこまで深掘りされず、申請から認証・登録までの大まかな流れを理解しているかを問う設問が多かった印象です。
審査及び判定規則
4種類ある審査の「判定区分」と、その後の「対応」の組み合わせを問う問題が複数出ました。
「どういう状態がどの区分にあたるのか」「その場合、事業者は次に何をすべきか」をセットで正確に頭に入れておく必要があります。
CO2排出量計算(体感5%):計算は必須
最後に、計算問題が数問出ました。私が受けた際は、ガソリン・電気の使用量からCO2排出量を計算し、それが温対法の報告基準である「原油換算1,500kl/年」を超えるかどうかを答えさせる問題でした。
排出係数は設問の中に記載されているので、数値を暗記する必要はありませんが、迷わず計算できる状態にしておくことが大切です。
これから受験する方への最短攻略アドバイス
もしあなたが「時間がない!何から手をつければいい?」という状況なら、最低限、以下の3つだけは完璧に仕上げておくことをお勧めします。
1. PDCAを構成する「14の要求事項」の暗記と流れの理解
2. 4種類の「判定区分」とそれぞれの「対応」の暗記
3. 主要なエネルギー(電気、ガソリン等)からの「CO2排出量」の計算方法
これだけで、合格ラインがぐっと近づくはずです。
この記事が、あなたのキャリアアップの助けになることを心から願っています。